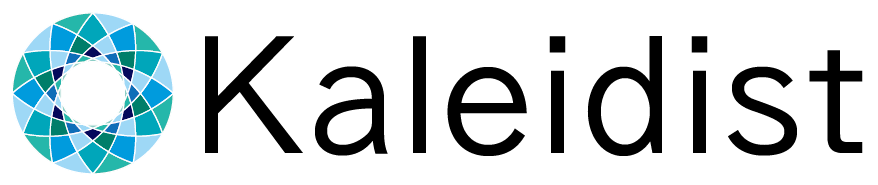「北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワークシンポジウム」開催報告
2月4日に北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク主催の「多様性を武器に これからの不確実な時代を生き抜くには ~ステークホルダーからのメッセージ~」と題したオンラインシンポジウムに、弊社代表の塚原が登壇しました。 大学や企業関係者を含め、約130名にご参加いただきました。
シンポジウムでは、4つの分野のステークホルダーがそれぞれの立場におけるD&Iの知見や学術的な見解をご講演いただきました。 D&I領域の専門家として弊社塚原、ミレニアル・Z世代の代表としてダートマス大学タック経営大学院に留学中の坪田駆氏、企業でのD&I実務家として株式会社JERAのダイバーシティ&インクルージョン推進室長の丸山昌子氏、そして男性学の立場から大正大学心理社会学部准教授の田中俊之氏の4名が講演しましたた。
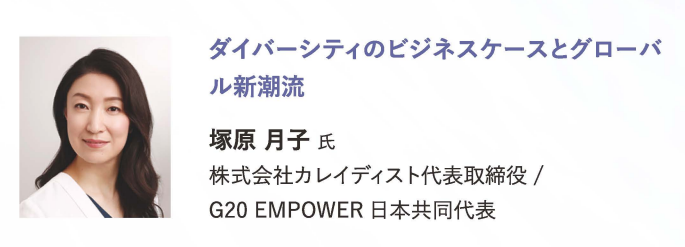
最初のスピーカーである弊社塚原からは、「ダイバーシティのビジネスケースとグローバル潮流」のテーマに、DE&Iの基本的な考え方、ダイバーシティの真の価値は多様性がマネジメントされてこそ発揮されることを説明しました。 DE&Iを推進するベネフィットとして、インクルージョンを感じる組織では構成員の幸せと組織への貢献が高まること、イノベーションを通じた組織業績の向上につながるといった調査結果などが紹介されました。 最後にグローバル潮流から見た日本の現況として、計画の策定や両立制度の整備などにおいて進捗が見られるものの、より徹底した測定管理や評価基準等への反映、それらを含めた経営層のアカウンタビリティ向上が課題であることを指摘し、締め括りました。
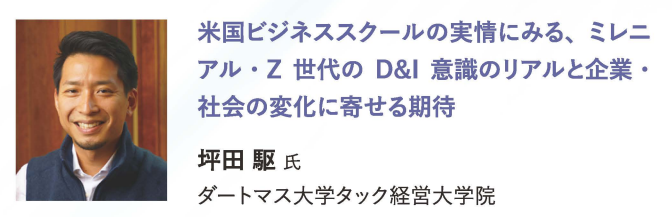
二番目のスピーカーの坪田氏からは、「米国ビジネススクールの実情に見る、ミレニアル・Z世代のD&I意識のリアルと企業・社会の変化に寄せる期待」と題して、アメリカのMBA学生のD&Iに対する意識の高さ、大学院としての取り組み、学生の企業選択に与える影響について語られました。 MBAではD&Iが関心の高いテーマの一つであり、D&Iの議論ができる場が整備され、D&Iの意識を高めたリーダーの輩出にも繋がっているという現状が説明されました。 ご自身がダートマス大学院の生徒会長に立候補されたご経験から、D&Iへの意識が高い候補者が多く、学内の様々な分断を取り除くことや自分がマイノリティという経験をしているからこそ見える改善提案等を訴えた経験を語られました。 同大学院では、DE&I推進の専門DEAN(学部長)が設置されており、ミッション、アクションプラン、KPIを対外的に公表、フィードバックを得て改善するというサイクルがトップの強いコミットメントで回されていること、また学生が主導するD&Iの取り組みも進んでいる状況が紹介されました。 そのような環境で学んだMBAの学生達は、自分たちのマイノリティ性にかかわらずリーダーシップを発揮し活躍できるチャンスがある企業への就職を見据え、企業のD&Iの取り組み姿勢を重要視していること、さらに、日本企業が次世代リーダー達にとって魅力のある職場であるためにはDE&Iの視点を持ったマイノリティ経験があるリーダーの登用が欠かせないと強調されました。
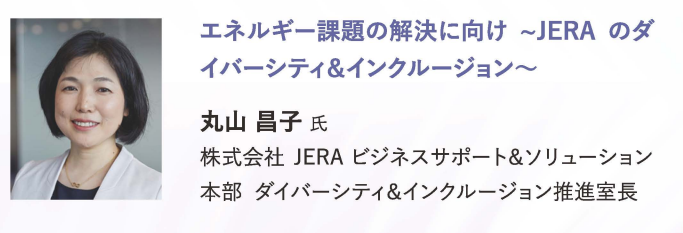
三番目のスピーカーの丸山氏からは、「エネルギー解決の課題に向け~JERAのダイバーシティ&インクルージョン~」と題して、自社のD&Iの推進策の主要な取り組みについて説明がありました。 JERAは業態特徴としても理工系学部出身者が多く、社員の女性比率が低いことを課題と認識し、積極的に女性の採用活動を行うとともに、意思決定層への女性登用を増やすために数値目標を設定し、計画的に機会を付与する施策を実施していること等について述べられました。 また、大多数を占める男性の行動変化を促すことを目的としたチェンジリーダープログラムを通じて、参加者がマジョリティの特権への気づきを持ったり、グローバル先進事例を踏まえて意識や行動に変化が見られることなどが紹介されました。 さらに、女性を対象とした意思決定層にかかわるキャリア形成を見据えたスポンサーシッププログラム、自分らしいリーダーシップのあり方を考える研修、育児中の女性社員のキャリア開発支援、持続可能な社会実現に向き合うグローバルリーダー育成を目的とした大学との連携など、女性人材パイプラインの強化を図っていることが紹介され、多様な人材が活躍できるカルチャーを根付かせ、イノベーションを起こす企業を目指すとの力強い言葉で締め括られました。
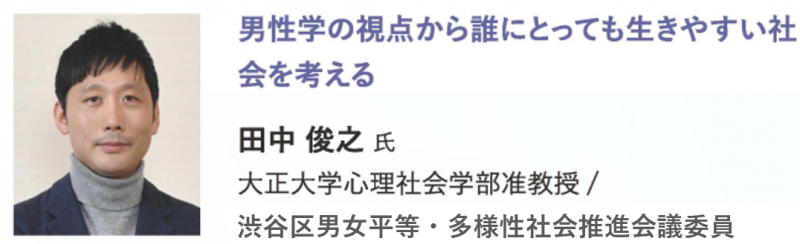
最後のスピーカーの田中氏からは、「男性学の視点から誰にとっても生きやすい社会を考える」と題して、D&I推進が置かれた立場によって受ける影響の違い、性別が自分の生き方に与える影響、積極的寛容と消極的寛容の違いについて語られました。 冒頭では「男は仕事、女は家庭 から 男も女も仕事も家庭も」のキャッチフレーズに潜む問題が提起されました。D&I推進のフレーズが、異性間で結婚して子育てしている家庭を前提としており、独身の人、シングル家庭、同性カップル、D&Iに理解のある職場環境で働けない人などの視点は考慮されていないゆえに、社会的に生じる苦痛や格差についても見落としてはいけないことを語られました。 また男性自身の当事者意識の足りなさゆえに、男女の賃金格差から助長される男性の働きすぎ問題や過労死、男性は定年まで働く前提に基づいた「平日昼間問題」のような無意識の偏見の問題が解決しないというご指摘がありました。当事者意識をもつ第一歩として、性別が自分の生き方に与えている影響を考えることの重要性が指摘されました。 最後に、多様性の包摂の実現に必要なものは、男性が上から目線で多様性を集める、活躍させるといった「やってあげている感」は問題外で、積極的寛容、つまり自分と異なる相手に敬意を持つという視点が大事で、お互いの価値観の理解のために面と向かって直接話す機会を考えていくことが、より大切になっていると締め括りました。