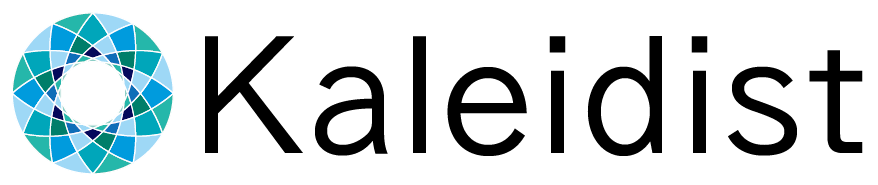カレイディスト・ニューズレター vol.5 - 2025年7月号-
2025年7月11日、「カレイディストニューズレターvol.5」を発行・配信いたしました。
「DEIトピック考察」については、HPでも公開しております。
今回は、上司の対話力とチーミング力を通じて、女性のキャリア形成の背中を押せる可能性をどう広げるのかを探っていきたいと思います。
上司の「対話力」がもたらす変化
パーソル総合研究所の調査*1によると、女性の管理職への昇進を後押しする上司の働きかけとして、「なぜ選ばれたのか」「どんな期待があるのか」「管理職になるメリット」を具体的に伝えることで、女性の挑戦意欲が高まるという。
自分にはリーダーシップが十分でない、女性活躍枠で自分が選ばれているだけなのではないか等、自信を持てない女性に対しては、これまでの仕事ぶりから管理職として十分やっていけるだけの経験やポテンシャル、適正があることを具体的に伝え、将来のキャリアを見据えた期待を示すことが重要だ。
その際には、グロースマインドセットの思考で、「今はリーダーとしてチャレンジかもしれないが、周囲に学びながらこれから成長できると思っている」と可能性への信頼を伝え、言われた側が“できるかどうか”ではなく、“やってみてもいいのかも”と思える言葉を伝えることが大事だろう。
さらに、管理職になるメリットとして、裁量が広がり、視座も高まることを伝えられると、前向きな一歩を後押しできるのではないだろうか。
管理職と子育てとの両立に懸念がある女性については、具体的な働き方の許容範囲、チーム内での支援方法を一緒に探ることで、”できるかも”と思える対話が欠かせない。

「チーミング力」が心理的安全性を育む
ある外資系のプロフェッショナルファームでは、メンバー同士が子育てや介護、自己研鑽のための時間の確保など、一見「仕事のカベ」になりそうな私生活で大切にしたいことをチーム内で共有し合う機会を、プロジェクト開始前に設けている。
「言いづらい個人事情」ではなく、「チームで配慮し合う前提」として位置づけるこの仕組みは、挑戦への安心感を生む土壌となっているという。
たとえば、男性マネージャーが私用の予定でカレンダーをブロックする姿勢を示すことで、「誰もが仕事以外の時間を大切にしていい」という共通認識がチームに自然と浸透。子育て中のメンバーも、送迎や家事のための時間確保を気兼ねなく行うことが“当たり前”になりつつある。
このように 肩書きにかかわらず、互いのないがしろにしたくないことを尊重し合うこの「チーミング」が、職場の心理的安全性を高め、個々人がより能力を発揮しやすい環境を築いている。
上司の一人ひとりが対話とチーミングの担い手となることで、女性も「やってみよう」と一歩踏み出す土壌が育まれ、誰もが“自分らしく挑戦できる”組織文化へと近づいていくのではないだろうか。それこそが、これからのマネジメントに求められる関わり方ではないだろうか。
出典:
- パーソル総合研究所:女性の管理職への昇進を後押しする上司の働きかけとは