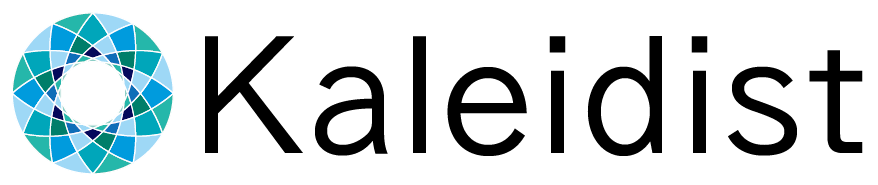カレイディストの最新ニュースと毎月プロの目を通じて見たDE&Iの様々なトピック、国内外の最新動向についての考察を月1回お届けしていきます。
News
日経xwoman連載記事『1周回ってDEIって何?』第5回が掲載されました
弊社のCEO塚原とCOO二木へのインタビューを元に記事化された、日経xwoman連載記事『1周回ってDEIって何?』の第5回、「全員が一言ずつ順番に話すだけ…無意味な経営会議 議論深めるには がリリー ...
日経xwoman連載記事『1周回ってDEIって何?』第4回が掲載されました
弊社のCEO塚原とCOO二木へのインタビューを元に記事化された、日経xwoman連載記事『1周回ってDEIって何?』の第4回、「職場で男女の垣根をなくすべき?」 経営と現場に大きなギャップがリリースさ ...
Newsletter
カレイディスト・ニューズレター vol.20 - 2026年新春号-
カレイディスト代表取締役社長兼CEO 塚原月子です。カレイディストでは、2026年もDEI推進のご支援を通じて、皆さまのありたい姿の実現に、そしてインクルーシブな社会の実現に貢献していきたいと願って ...
カレイディスト・ニューズレター vol.9 - 2025年12月号-
皆様、こんにちは。今月もカレイディストのニューズレターをご覧いただき、誠にありがとうございます。気が付けば今年も師走を迎え、慌ただしい毎日が続いていることと思います。皆さまにとって実りある一年であ ...